「ただいま〜〜」
疲れた色は隠せず、ミューズは、低い声で帰宅の声を潜った玄関口であげる。
「おかえりなちゃい!ダディ!マミィ!!」
ぱたぱたと忙しい足音を響かせ、居間から飛び出し、廊下を走ってくる、
愛娘の姿に、ふたりは微笑む。
アスランの刷り込みが成果をあげたのか、すっかり、両親である、ふたりを
呼ぶ時は、この名称が定着してしまった。
帰宅し、愛娘の出迎えを受ける、この時を迎えられることが、イズミとミューズに
とっては、なによりも幸せを感じる瞬間。
ぴょ〜ん、と飛び上がり、サクラはイズミの身体に飛びついてきた。
刹那。
二階から響く、騒がしい物音に、ふたりは顔を見合わせた。
「アァーーースラァァーーーンッ!!」
カガリの凄まじい叫び声が、下階までモロ聞こえ。
同時に聴こえる音は、どう耳を澄ませても、扉を蹴ってる音にしか聴こえない。
「・・・サクラ?二階が随分騒がしいけど、なにやってるんだ?」
幼子を腕に抱いたイズミは、眉根を寄せ、腕のなかの少女に尋ねる。
二歳になったばかりの少女は、実に闊達に説明をする。
「パパが、お部屋に閉じ篭って出てこないの。ママ、怒っちゃって、どかどかドア、
蹴ってる。」
「・・・」
「・・・」
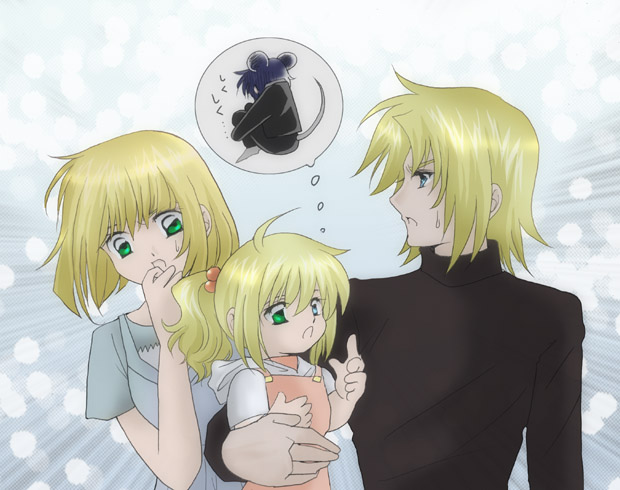
サクラの言葉を訊き、ミューズとイズミは、顔を見合わせ、冷や汗を一筋零した。
・・・十中八九、なにかがなければ、アスランの悪い癖はでないはずだ。
ということは、なにかがあったから、現状がこうなのだろう。
さて、その原因は、なんなのか。
サクラを居間で降ろし、フローリングの床で、玩具と戯れる双子の面倒を頼み、
イズミとミューズは、二階に続く階段を登っていく。
首ひとつ分、階段の上り口から覗かせ、ふたりはまた顔を見合わせた。
階段から、すぐの部屋は、アスランの書斎。
その前で、カガリは、ドアを手のひらで激しく叩いている。
「いい加減にしろッ!!子供じゃあるまいしッ!!」
だが、カガリの問い掛けには応えず、部屋は無反応。
うんとも、すんとも云わない。
恐らく、主が在室しているのに、返事を返さない状態なのだろう。
「もう、知らんッ!勝手にしろッ!!この、馬鹿ネズミッ!!」
ドカッ!!
止めの、カガリのひと蹴りに、扉がたわむ。
鼻息荒く、カガリが階段に向かってくる姿を認め、ふたりは慌てて下階に下りた。
なに喰わぬ顔で、ダイニングの入り口で、帰宅の挨拶をすると、カガリはふたりの
顔を見た途端、派手な溜息を漏らした。
「・・・なにか、あったの? お母さん。」
三人で、ダイニングテーブルの椅子に腰掛ながら、ミューズは問う。
無言で、ふたりの前に差し出されたのは、一通の封筒。
蝋封がされ、それが、『なにか』の正式な書簡であることを伺わせた。
「開けて良い?」
ミューズの確認の声に、カガリは視線も合わせず、テーブルに片肘をつき、
頬を支え、呆れた風体のまま頷く。
開封した内容文に、イズミとミューズは一緒になって、視線を落とす。
「結婚式の招待状!?」
ミューズは、僅かに驚いた声をあげる。
「ああ、ディアナのな。」
ようやっと口を開いたものの、カガリの声は、当然の如く、不機嫌。
「アスランと私、夫婦ふたりで出席してくれ、ていうのに、アスランの馬鹿たれが、
いじけて篭城しちゃって、にっちもさっちもいかなくてな・・・ まったく、どうにか
なんないか? あれ。」
「・・・どうにか、って。 お母さんが言ってダメなら、私たちなんかもっとダメに
決まってんじゃない。」
ミューズは、視線をあげ、母親の顔を見遣る。
上手い打開策も見つけられず、ダイニングルームに暗い沈黙が漂う。
「あ! お茶でも飲みますか? お義母さん。 ミューも飲むだろ?」
場の空気を換えようと、気を使ったのか。
イズミは椅子から立ち上がり、キッチンに向かう。
ふたりのお気に入りにしている、茶を用意し、ダイニングテーブルに置くと、
カガリは、礼を述べ、美味そうに茶を啜った。
「すまないな、イズミ。 もう、怒鳴り過ぎて、喉カラカラだ。」
苦笑を浮かべるカガリを見、イズミも苦笑いを洩らす。
「貴方、ホント、お茶の入れ方、上手い。 とっても美味しいわ。」
イズミに対し、ミューズも素直に褒め言葉を零すのに、彼は優しく笑む。
「いつでも云ってくれ。 お茶くらいなら、いくらでもいれるから。」
彼の返事を訊き、カガリとミューズは、緩い笑みを零した。
「しかしな〜 どうしたもんか。 仮に欠席の返事をした処で、まさか理由が
『篭城』とは書けないしなぁ〜〜」
カガリは、溜息に暮れながら頬杖のまま、呆れた視線を空に投げる。
母親の、そんな姿を見、ミューズは閃いた、という顔でカガリに問うた。
「だったら! 私たちが、お母さんたちの名代で、出席、というのはどう?
ほら、イズミも私と結婚してから、一度も里帰りしてないし、それも兼ねて。」
「・・・」
カガリは、娘の発案に金の瞳を開く。
「唯、サクラは連れて行くけど、ツルギたちは、まだ長旅はきついと思うから、
みててもらうことになっちゃうけど・・・。」
「ふむ。」
カガリは、提示された意見に、前向きな検討を打ち出す。
許諾の期待を込めた、ミューズの視線を受け止め、カガリは苦笑を洩らした。
「どのみち、どんなにこっちが騒いだって、アスランは動かないだろうからな。
お前たちに頼むか。」
頷き、ミューズは笑顔を作る。
が、この意見に、もっと喜んでくれるかと思っていた、イズミの反応は、ミューズの
考えとは僅かに掛け離れていた。
「・・・あの〜 本当に、良いんですか?」
遠慮を含んだ、イズミの声に、カガリは身体を椅子の背に預け、笑む。
「私たちに気を使うことはない。『婿』ということに、気を捉われ過ぎることはないぞ?
イズミ。 この家に来た時から、貴方も、私たちの家族になったのだからな。」
「は、はい! ありがとうございます!!」
余程、安堵したのか、イズミは久し振りに帰ることを許された、郷里への思いに、
弾んだ声音を返した。
事が、決定されれば、実行は早い。
イズミとミューズは、準備を整え、旅程の組みたてに入った。
その間も、アスランが部屋からでてくることはなく、時間於きに差し入れられる
食事のトレイが、部屋の前に置きっぱなしにされたままなのは、ふたりがオーブを
旅発つ日まで改善されることはなかった。
心配げな視線で、ミューズは見送りにでてくれた、母親の顔を見詰めた。
「お父さんのことは、心配するな。 時間が経てば、もとに戻るから。 お前の時も
そうだったろ?」
頷き、ミューズは玄関先から、父親の書斎に当たる部屋に視線を送る。
カーテンくらい、開けて、見てくれるかも・・・
だが、期待虚しく、それもなされる事無く、ぴったりと閉じたカーテンを見て、ミューズは
息をついた。
「じゃあ、行ってきます。 ツルギとヒビキのこと、お願いします。」
「ああ、心配するな。 久し振りの旅行だし、親子水入らずで楽しんでこい。」
「ママ、バイバイッ!」
イズミの片腕に抱かれ、サクラは可愛らしい、白のワンピースに身を包み、ご機嫌。
元気にカガリに対して、手を振っている。
それに合わせ、イズミも頭を垂れた。
アスハのお抱え運転手が、運転する車が三人の前に滑り停まる。
車に乗り込み、専用機が待機している空港まで送られ、あとは飛行機が飛び立つのを
待つだけ。
初めて経験する、空の旅に、サクラは終始、はしゃぎっぱなし。
ミューズも、イズミも苦笑を浮べ、その様子を見守った。
10時間余りの、空の旅は、実に快適で、文句のでようはずもない。
使用されたのは、アスハの専用機。
ジャンボジェットを改良した機体なので、内装は、アメリカの大統領専用機、エアフォースワン
をも上回る、豪華さ。
ゆったりとしたリクライニングシートは、ちょっとしたシングルベット感覚だ。
広い機内では、必要な座席数しか設置されていないので、さながら空飛ぶホテルとも云えよう。
手が空いた客室乗務員は、サクラにとっては、格好の遊び相手。
鬼ごっこを強請られ、始めのうちこそ、ミューズたちの顔色を伺っていたが、逆に遊んでやって
欲しい、などと云われれば、普通にお姉さん、お兄さんという、感覚の年上の遊び相手となる。
退屈することもなく、楽しく空の旅を終えれば、今度は、機体を降りる時にサクラの方が
ぐずってしまうことに手を焼いてしまう。
「また、帰りにも、この飛行機で帰りますから。その時に遊びましょう、サクラ様。」
乗務員の女性に促され、サクラは渋々、握っていた、制服の上着を離す。
「では、5日後に、また。」
ミューズは、サクラを腕に抱き、乗務員と見送りにでてきた機長に言葉を掛ける。
「かしこまりました、ミューズ様。」
頭を下げ、機長は笑顔で返事を返す。
「行きましょう、イズミ。」
立ち並んだ、彼に声をかけ、ミューズはタラップを降りていく。
「イズミ様も、お気をつけて。」
「ありがとう。」
細やかな気遣いに感謝し、ふたりは、王宮からの迎えの車に乗り込んだ。
「先に、兄上の所に寄りたいんだけど、良いかな?」
ミューズに問い尋ねれば、あっさりとした許諾が返ってくる。
「全然、構わないわよ?」
笑顔での答えを聞き、イズミは行き先の変更を運転手に告げる。
車は、彼の指示に従い、イズミの兄、クトレの宮を目指す。
「なんか、すごく、懐かしい。」
車窓から、外の景色を眺めていたミューズは、眼を細め、感慨に耽っていた。
「そう?」
イズミは、緩く笑み、彼女の顔を見遣った。
「サクラ、よく見ておきなさい。ここが、ダディが生まれた国なんだから。」
「うん!」
ミューズに促され、サクラは車の窓にへばりつく。
幼子の、その後ろ姿を見、ふたりは、優しく、嬉しげな瞳で顔を見合わせたのだった。
Back 戻 Next